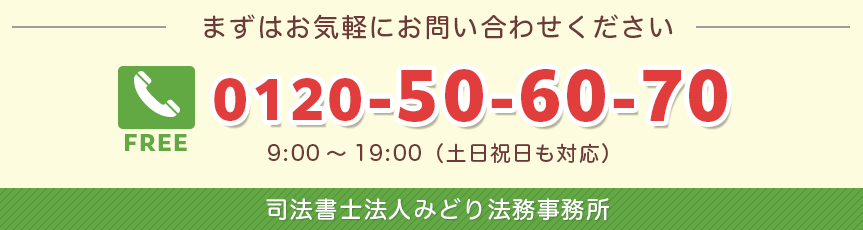債務整理後はクレジットカードの利用が制限されます。信用情報への影響期間や回復方法、代替手段について詳しく解説します。
債務整理が信用情報に与える影響
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されます。日本には主に3つの信用情報機関があり、CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)がそれぞれ異なる業種の金融機関から情報を収集しています。
任意整理の場合、「債務整理」や「弁護士介入」などの情報が登録され、登録期間は完済から約5年間です。個人再生や自己破産の場合は、「民事再生」や「破産」などの情報が登録され、CICとJICCでは5年間、KSCでは10年間登録されます。
信用情報に事故情報が登録されている間は、新たなクレジットカードの作成や各種ローンの申込みが困難になります。これは金融機関が審査の際に信用情報を照会し、事故情報があると返済能力に不安があると判断するためです。
ただし、信用情報の登録期間は債務整理の種類や信用情報機関によって異なります。任意整理の場合、完済から5年経過すれば情報が削除されるため、その後は通常通りクレジットカードの申込みが可能になります。
自己破産の場合、免責許可決定から5年(KSCは10年)で情報が削除されます。個人再生の場合は、再生計画の履行完了から5年(KSCは10年)で削除されます。これらの期間は法的に定められているため、期間経過後は自動的に情報が削除されます。
信用情報機関では、本人が開示請求を行うことで、自分の信用情報を確認することができます。開示請求は郵送、窓口、インターネットで行うことができ、手数料は500円〜1,000円程度です。債務整理後の信用情報回復の状況を確認するために、定期的に開示請求を行うことをおすすめします。
債務整理後のクレジットカード利用と代替手段
債務整理後にクレジットカードが作れない期間中でも、生活に必要な決済手段を確保する方法があります。デビットカードは銀行口座から即座に引き落とされる仕組みのため、信用情報に関係なく作成できます。
デビットカードには、J-Debitとブランドデビットの2種類があります。J-Debitは日本国内の加盟店でのみ利用できますが、ブランドデビット(Visa デビット、Mastercard デビットなど)は世界中のVisa、Mastercard加盟店で利用できます。ネットショッピングや海外利用も可能なため、クレジットカードの代替手段として非常に有効です。
プリペイドカードも有効な代替手段の一つです。事前にチャージした金額の範囲内で利用でき、審査不要で作成できます。Kyash、LINE Pay カード、au PAY プリペイドカードなど、様々な種類があります。
家族カードという選択肢もあります。配偶者や親などの家族がクレジットカードを持っている場合、その家族カードを作成してもらうことで、クレジットカード機能を利用できます。ただし、利用額は本会員の与信枠内となり、利用明細も本会員に送付されます。
電子マネーやスマートフォン決済アプリの活用も重要です。Suica、PASMO、nanaco、WAON、楽天Edy、iD、QUICPay、PayPay、楽天ペイ、d払いなど、多くの選択肢があります。これらは現金やデビットカードからチャージして利用できるため、債務整理後でも問題なく利用できます。
信用情報が回復した後のクレジットカード申込みでは、いくつかの注意点があります。まず、債務整理を行った金融機関の系列会社では、社内ブラックリストに残っている可能性があるため、審査に通りにくい場合があります。
最初は年会費無料のカードから申込むことをおすすめします。楽天カード、イオンカード、エポスカードなど、比較的審査に通りやすいとされるカードから始めて、利用実績を積んでから他のカードに申込むという段階的なアプローチが効果的です。
短期間に複数のカードに申込むと、審査に悪影響を与える可能性があります。申込み情報は6ヶ月間信用情報に記録されるため、1つのカードの審査結果を確認してから次の申込みを行うことが重要です。
信用情報の回復を早めるためには、携帯電話の分割払いや奨学金などの支払いを確実に行い、良好な支払い履歴を作ることが有効です。また、銀行口座の管理をしっかりと行い、公共料金の支払い遅延なども避けることが大切です。