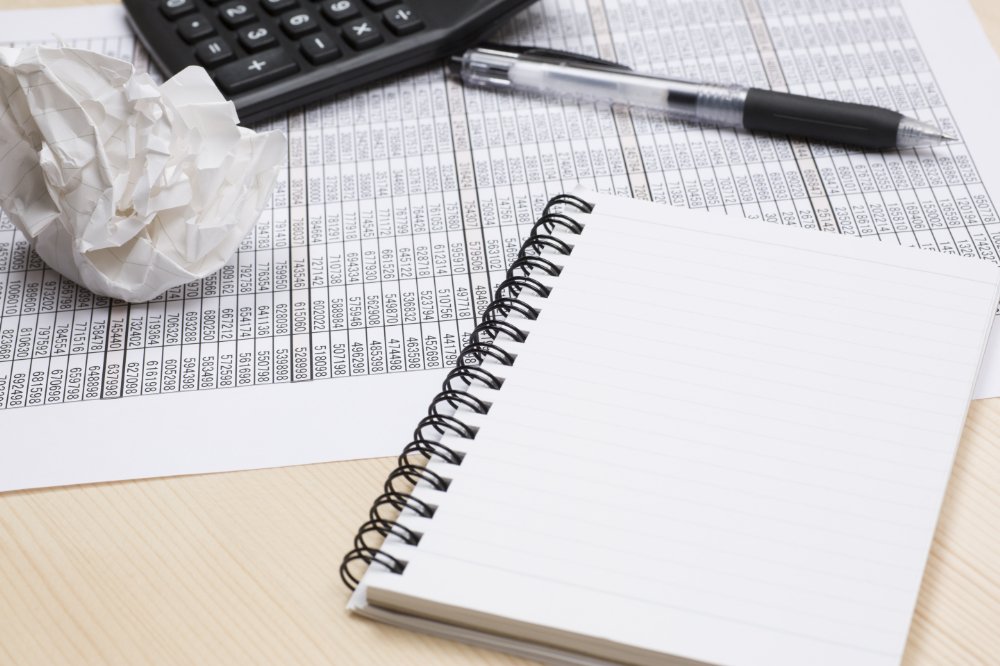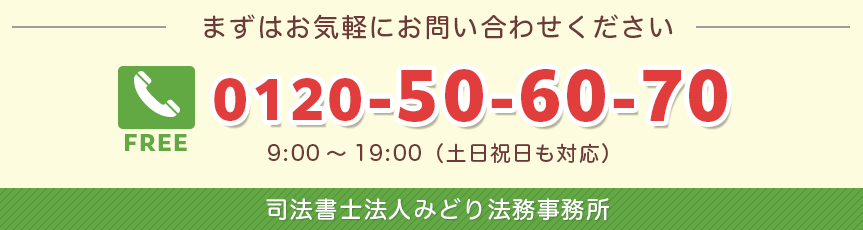個人再生は住宅ローンがある方でもマイホームを維持しながら借金を大幅に減額できる債務整理方法です。住宅資金特別条項の活用方法について詳しく解説します。
個人再生と住宅資金特別条項の基本
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう債務整理の方法です。自己破産とは異なり、財産を手放すことなく借金問題を解決できるのが最大の特徴です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みがある個人が利用でき、債権者の過半数の同意が必要です。給与所得者等再生は、給与所得者などの安定した収入がある方が利用でき、債権者の同意は不要ですが、可処分所得の2年分以上の返済が必要となります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、個人再生の大きなメリットの一つです。この制度を利用することで、住宅ローンはそのまま支払いを続けながら、他の借金のみを大幅に減額することができます。
住宅資金特別条項を利用するための要件は厳格に定められています。まず、住宅ローンの対象となる建物が債務者の居住用であることが必要です。事業用や投資用の不動産は対象外となります。また、住宅ローン以外の担保権が設定されていないことも要件の一つです。
住宅ローンの支払いが滞っている場合でも、個人再生の申立てまでに滞納を解消すれば、住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。ただし、保証会社による代位弁済が行われてから6ヶ月を経過すると利用できなくなるため、早めの対応が重要です。
個人再生では、借金の総額に応じて最低弁済額が決まります。借金総額が100万円未満の場合は全額、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満の場合は借金総額の5分の1、1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、3000万円以上5000万円以下の場合は借金総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅を残すための具体的な手続きと注意点
住宅資金特別条項を含む個人再生の申立てを行う際は、通常の個人再生申立書に加えて、住宅資金特別条項に関する書類も提出する必要があります。住宅ローン契約書、登記簿謄本、住宅の評価額を示す資料などが必要となります。
住宅ローンの返済条件を変更する場合は、期限の利益回復型、リスケジュール型、元本猶予型、合意型などの方法があります。期限の利益回復型は、滞納分を分割して支払うことで通常の返済に戻す方法です。リスケジュール型は、返済期間を延長して月々の返済額を減らす方法です。
元本猶予型は、再生計画の履行中は利息のみを支払い、元本の返済を猶予する方法です。合意型は、住宅ローン債権者と合意した内容で返済条件を変更する方法です。債務者の状況に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
住宅の価値が住宅ローン残高を上回る場合(アンダーローン)は、清算価値保障原則により、その差額分を最低弁済額に上乗せする必要があります。逆に住宅ローン残高が住宅の価値を上回る場合(オーバーローン)は、清算価値への影響はありません。
個人再生の手続き中も住宅ローンの支払いは継続する必要があります。支払いが滞ると住宅資金特別条項の取消しや個人再生の廃止につながる可能性があるため、確実に支払いを続けることが重要です。
再生計画の履行期間は原則として3年ですが、特別な事情がある場合は5年まで延長することができます。この期間中は、住宅ローンと再生計画に基づく返済の両方を行う必要があるため、十分な収入があることが前提となります。
住宅資金特別条項を利用した個人再生は、マイホームを守りながら借金問題を解決できる有効な方法です。ただし、要件が厳格で手続きも複雑なため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。早期の相談により、最適な解決策を見つけることができるでしょう。